
| [舞-HiME] |
| 世界の果て | |A5変形|P20|¥200| |
 |
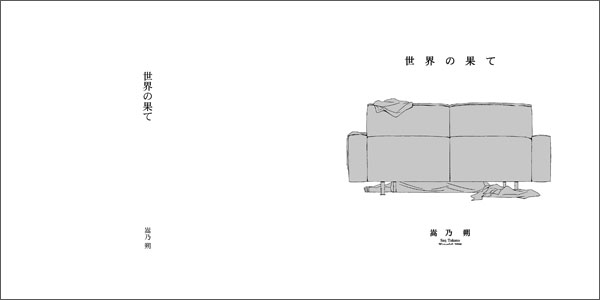 |
|
「なあ、なつき?」 いつもと変わらぬ声。 京都弁特有のおっとりした言葉使いと気遣うような優しげな声音。 斜めに読んでいた雑誌から顔を上げて振り向くと、どこか企んでいるような色の目。――最近は流石に、何か含むものがある時とそうでない時との区別もつくようになった。付き合いも随分と長いのだから当たり前と言えば、当たり前なのだが、昔は本当にそれが分からなかった。取っ付き易そうに見えて存外深い所までは他人を立ち入らせなかったりと、彼女自身ガードが固かった所為もあるが、わたしの方が彼女のそういう質すら理解出来ないような鈍感な感性の持ち主だったのが、その主な原因だ。 何を考えているか分からない。 否、分かろうともしなかったし、肝心な所で二の足を踏んでいた。 静留にだけはそれなりに心を許していたように思うが、それはわたしの思い込みというか勘違いで、肝心な所で、他人の深い部分から目を逸らしてばかりいた。他人に対しては言わずもがなだが、彼女に対しても然り、だったのだ。 だから、彼女のわたしに寄せる想いなんて知る由もなかった。 「なんだ? 静留」 わたしは振り向きつつそう彼女に声を掛けたが、彼女の顔を見た途端、甘えたそうだな、と思った。 「なつき」 彼女はもう一度わたしの名を呼ぶと、やはり、欲するようにわたしの首に手を添えて来たのだった。 そしてそのまま、ソファーで寝転がって踏んぞり返るわたしの背後から 顔を寄せて来て、キスをねだった。 わたしは顎を上げて、それに応じた。 ただ、触れるだけのキスかと思ったら違った。いきなり深く舌を差し込まれる。わたしはキスに応じながら身体をひねって上半身を彼女の方へ向けた。口の中で静留の舌を感じる。絡み合う音が口の中で響いた。 ――長いな、と思ったら、手が胸に触れた。 思わず反射的に唇を離していた。 「おい! いきなり何を…」 「だめ……なん?」 静留はちょっと首を傾げて、甘えてみせた。以前は甘えるにしてももう少し静留らしかった、というか駆け引きのようなものがあったが、最近はそれすらない。ただ甘えるだけだ。 付き合い出したばかりの頃は、わたしにその気がないならないなりに、押して駄目なら引いてみろとばかりに、寂しそうな顔をしてみせ、渋るわたしをなんとかベッドまで行かせたものだが――それから1年。お互い色々な物をさらけ出して来たその歳月で、妙な駆け引きも通用しなくなった。その分、こんな風に妙な素直さでアピールしてくる事もままあり、さてどうしたものかと思案した。 「……というか、いきなりどうしたんだ。って、おい、手を……!」 わたしは静留の手を払い除け、抵抗してみせる。 だが――実の所、こんな静留も決して嫌ではないのだ。寧ろ可愛いとさえ思う。稀に見せるこんな無邪気さが、自分にだけ向けられているのかと思うと、愛おしくてたまらなくなったりもする。静留はこんな風に子供じみた表情は、決して他人には見せたりしないのだから。 否、他人にはしないというより、わたしと二人きりの時間が増えたからこそ、こういった表情をする事を覚えたのだろう。――わたしの自意識が過剰でなければ、きっとそうなのだ。 でも、子供のようににこにこしながら、――それでいて、やっている事と言えば大人の戯れのそれだったりするのだから、呆れて溜め息の一つも出るし、何せ、大人しそうな顔をして結構えぐい事までしたりするのだから、この笑顔に騙されてはなるまいと、取り合えず抵抗してしまうのだ。 「な……なつき?」 「…………」 静留は今度はやんわりと頬に触れる。 彼女はなんだかんだと、無茶な強要はしなかった。わたしが少しでも応じるような素振りを見せれば、ここぞとばかりに自分のペースに持ち込み、もう否とは言わせないが、わたしが頑として拒めば無理強いはしなかった。 今ならそれが、彼女の優しさであり、弱さだと分かる。 わたしへ対する愛情の深さ故に、弱りもする。万が一にもわたしに嫌われるのが怖いのだろう。 彼女は以前、意識のないわたしを抱いた。わたしたちの関係はあの時とは変わっていたが、それでも気安い思い出話などにはまだ出来ない。――わたしにとってではなく、彼女にとって。 わたしはあの時の彼女の心情など推し量る事しか出来ないし、それを敢えて聞こうとも思わない。少なからず、あの時の行為が彼女の枷になっているのが分かるから。これ以上、無碍に彼女を傷つけたくはなかった。 過ぎた事だと割り切れないのだ、静留は。 過去は過去と割り切ってくれたなら、どんなに楽になる事だろう。 少なくともわたしには咎めるつもりなんて、端からないというのに。それは分かっていると、いつも弱々しく首を振るだけだ。 それが彼女の弱さとなる。 強く求めたってわたしは壊れやしない。それを分かって欲しいのに、肝心な所で弱いのだ、――わたしたちは。 「静留」 わたしは静留を引き寄せると、ソファに彼女を組み敷いた。 いつの間にか日が落ちていた。 薄暗くなった部屋で、彼女の肩が微かに震えた。互いの肌が触れ合っている箇所は驚く程熱かったが、それ以外は少し肌寒かった。ベッドでなら毛布を引き寄せる所だが、生憎とリビングのソファの周りにはそんな物はない。 「寒いか? ……そろそろ服を着るか」 独り言のように呟いて起き上がろうとすると、上になった彼女が抵抗した。 「もうちょっと、……このままが、ええわ」 そう言ってわたしの胸に擦り寄って来る。そしてゆっくりと目を閉じた。 もうすぐ夏も近い。 静留がいいと言うならまだいいかと、わたしも全身の力を抜いた。 それにまだ気怠かった。下腹部がじわりと痺れている。 それに――、 もう少しの間――、触れ合う素肌の熱と彼女の重みを、味わっていたかったから。 わたしも目を閉じ、ほうっと息をついた。触れ合う肌。お互い全裸だから、様々な箇所が密着している。 ふと、たわいもない事に気が付き、静留に気付かれないように口元だけで苦笑した。 数年前には、誰かとこんな風に一糸纏わぬ姿で平然と抱き合うなんて考えられなかった。今だって少し気恥ずかしい。今は……、「直後」だから余韻があるからまだいいとして。どちらかと言えばいざ服を脱ごうという瞬間の方が恥ずかしい。 ――……何を言い訳してるんだ。 わたしは今度は盛大に溜息をつき、彼女の髪に鼻先を埋めた。 ふわり、と彼女の柔らかな髪の匂いが鼻先に漂う。 ……ああ、この匂いが好きだ、と思った。そのまま彼女の髪に触れようとして、はたと気付いてその手を下げた。――後で風呂に入るとは言え、彼女を弄った手で髪に触れるのは躊躇われた。 その手を彼女の腰へ回し、背骨のラインを無造作になぞる。細いウエストは柔らかく、優しかった。 「……ん」 彼女が身じろぐ。 「くすぐったいか?」 そう尋ねても、返事はなかった。その代わりくすりと微笑んで、わたしの胸の上辺りにキスをした。 わたしも力無く小さく笑う。彼女のそんな仕種が可愛らしく思えて仕方がない。 わたしは手の動きを止める事なく、ウエストを撫で続けた。撫でさすっているととても落ち着いた気分になってくる。 静留もそれが気持ちいいのか、もう一度頬を擦り寄せると小さく息をついた。そんな仕種がまるで――デュランのようでおかしかった。わたしは愛犬を撫でるような気持ちになって、更に彼女を撫で続けた。 穏やかな表情を見せる彼女を見ていると、不思議なもので、それだけで満たされた。誰かと同じ時間を共有する。――こんな風に、ゆったりと、何をするでもなく。 こんな穏やかな安らぎ方があるのだと、 曾てのわたしは知らずにいたのだ。 昔は、彼女は日溜まりの中にいるものだと思っていた。 こんな風に穏やかに笑って、陽のあたる場所で皆の輪の中心にいるのだと。 あの頃は色々な事が分からなかった。色々な事が見えなかった。 尖って他を寄せ付けず、自分は孤独であるものだと思い込んで。だから彼女は――静留は自分とは違う世界にいるものだと思っていた。 陽のあたる場所だというイメージは、恐らく実際に彼女が学園の中庭で仲間らと過ごしていたからそう思ったのだろう。緑の芝生に腰を降ろして皆で何かたわいもない話をしていた。それがとても眩しく見えていたのだと思う。――当時のわたしはそれが眩しいだなんて、決して認めやしなかったが。 陽のあたる場所。 藤乃静留はそちらの世界の住人だと思っていた。 透明なガラスの向こうの住人。こんな風に穏やかに笑える人間は、きっと本当はガラスの向こう側にいて、ショーケースに陳列された商品サンプルみたいなもので、掴もうと手を伸ばしてもガラスにぶつかるだけで、ただこちらが馬鹿を見るのだと、そう思い込んで差し伸べられた手を払いのけてばかりいた。 それに、何故手を差し伸べて来るのか分からなかった。 わたしに興味を示す者など、大概は一度突っぱねてしまえば二度と好んで拘わろうとはしなかったし、それが当然だと思った。それほど冷徹に他者をあしらった。わたしは他人との拘わり方を知らず、教師ともクラスメートたちとも、程よい距離の取り方が分からずに、うまくいかないと反って撥ね除けてばかりいたので、いつしかそれを当然の事なのだと思い込んでいた。――世界はそういう風に出来ているのだと。他人を信じて馬鹿を見るのは自分なのだと。 ――でも。 彼女が。 静留が。 わたしを。 こんな風に。こんなにも。 変えてくれたのだ。 「静留」 「…………」 わたしが呼びかけると、彼女はデュランよろしく無言で視線だけを上げる。 そんな仕種が愛犬の姿とだぶり、信頼されているのだなと妙に実感してしまう。 「何でもない。呼んでみただけだ」 そう言うと少し首を傾げてまた胸元にキスを落とされた。 そう――、 いつの間にか、差し伸べられた手が、それが一時の気紛れなどではなく、その手を掴んでも振り払われることはないのだと信じられるようになっていた。初めて触れた手がとても暖かかったのを覚えている。 ――綺麗な手ぇしてはるね。 そんな風に言って、とてもさり気なくわたしに触れたのだ、静留は。 誰かに髪や体形を褒められた事は何度もあった。その度に、なんと言っていいか分からず、そうか、と素っ気無く答えると、もうそれ以上は何も言って来なくなったりして、会話はそれ以上続かなかった。だからわたしは何も言わずに去るしかなかったのだ。 だからあの時も、素っ気無く、だから何だと問い返してやった。すると静留が御多分に漏れず微苦笑したものだからそのまま去ろうとしたら、うち、あんたの手ぇ好きやわ、などと歯の浮くような事を言われ思わず足を止めたのだ。そして一度振り払った筈の手を取られ、それがとても大事な物であるように優しく握られた時に、人の手はとても暖かいのだと知った。 せやから、たまにうちとこうして話さしてな。 わたしは面食らった。 は、――はあ? 何を言っているんだ。話するのに何の関係がある! せやけどこうして会っとれば、手も触れるやない。 ば、馬鹿馬鹿しい。詭弁だ。というか、気安く触るな! いややわ。なつきのいけず。 貴様! ――誰が名前で呼んでいいと言った! 名前呼ぶのに許可がいりますのん? そうだ! ならうちの事は静留でええから、あんたの事も名前で呼ばしてくれへん? ふざけるな。誰が―― あの時から静留は変わらない。人を煙に巻くのが上手いのだ。まんまと乗せられて……それが嫌な感じがしないのだから質が悪い。 だからいつの間にか、自然と、少しずつ少しずつ、わたしの中で彼女の占める割合が多くなっていった。擦れ違う回数、言葉を交す回数、会う回数、側にいる時間。そんな風に少しずつ――。 気付いたらわたしは彼女の取り巻きたちにすら「静留お姉さまと仲の良いちょっと恐い人」のレッテルを貼られていた。不思議とそんな風に陰で何か言われても悪い気はしなかった。何か噂以上の被害があった訳ではないし、――恐い人、というのも否めなかったし。静留は学園では既に有名人の一人だったし、正直な所多少の優越感がなかった訳ではないのも、確かだ。 静留を受け入れた事で、わたしが望むと望まざるとに関わらず他人との関わりも少なからず増え、人との距離の取り方も覚えた。 そんな風に、わたしは彼女と一緒にいる事で、少しずつ変わっていった。 彼女は確かに一度、わたしを傷つけたのかも知れない。確かにあの時のわたしは僅かの間だけでも自分を被害者のように感じていた。 あの時の事を罪だと言うのなら――否、彼女にとっては罪なのだろう。でも罪だとしても、それが、それこそが何も取り繕ったりしない静留の姿なのだとも思う。 今なら、――今だからこそ、そう思う。日溜まりの陰の暗い影。一見強かに思える彼女の本質は、寧ろそちらの弱さの方にこそあるのかも知れない。普段は穏やかな部分しか人に見せないが、そうして賢明に隠した暗い部分も確かにあって、それら全てで藤乃静留なのだ。 あの時―― なんだか良く分からないが、自分の中の何かを汚されたと思った。彼女の手がわたしの頬に触れた時、その余りの冷たさにそれが誰か知らない人間のもののように思われた。背筋を嫌なものが這い上がった。兎に角訳が分からず気持ち悪かった。彼女の手が、ではなく、その現状が。自分の知らない所で、何か『良く分からないが重大な事』が起ったようで、更にそれが性的なものであり、それが静留の手で行われたという事が、ただもう良く分からなかった。 だが、雨の中倒れ、再び病院で目を覚ました時、舞衣を追う楯を見て、自然と静留の顔を思い出し穏やかな気持ちになったのだ。ああ、そうか、静留はわたしが好きなのか、と。 静留はわたしが好きなのだ。 そうだ。わたしも静留が好きなのだ。――そう思い出していた。 今とは違った情愛――親愛ではあったが、彼女が邪だと言った部分を見せつけられても、戸惑いこそすれ、絶対に嫌いになんかなれなかった。――絶対に。 だから、彼女を止められるのは――彼女を止めるのは自分だけだと思った。――止めたかったのだ、彼女の痛みを。 思えば、わたしは彼女の微笑む顔しか知らなかったのだ。笑顔で、わたしを待っていてくれた。そんな静留しか知らなかった。 ずっと、辛抱強く。こんな、わたしを。 辛抱強く。 「……ああ」 ――静留は、 「…………何どす?」 「……いや、」 日溜まりの中にいたんじゃない。 「多分……」 わたしにとって、 彼女が日溜まりのようなのか。 「いや、……何でもない」 「もう。さっきから、そればっかりやね」 静留は怒ったふうでもなく、いつもと変わらぬ笑顔ではんなりと笑った。 優しくて暖かくて、わたしにとってはとても眩しいその笑顔で。 ――なつき、 そう呼ぶ声はとても優しくて。 ……なつ……き、 あの時わたしの名を呼んだ声は、とても、悲しくて。 でも。 「静留」 「ん……何?」 三度ゆっくりと静留が顔を上げる。ほんの少し眠そうな目をしている。 「……このまま寝たら、風邪をひくぞ」 わたしがそう言うと、小さな笑みを浮かべてぽそりと呟いた。 「ええよ。……なつきとなら」 わたしは、冷えた彼女の肩を抱いた。 小さな間違いや喜びや悲しみも、――その全て忘れずにこのまま行こう。 孤独だった過去のわたしも、お前とわたしが犯してしまった罪も、傷ついた事も、それが全てで、わたしたちなんだから。 静留。 どこまでも。 ふたりで。 多分。 世界は、 わたしが思っていたよりも、 ずっと ずっと――ひかりに満ちているのだから。 END |
| あとがき |
| ★2006年5月3日発行 ★「世界の果て」は同人誌で頒布した作品です。 |