|
SAMPLE |
| [オリジナル百合] |
| アコガレノキミ 【成人向け】 |
|A5|P52|¥600| |
 |
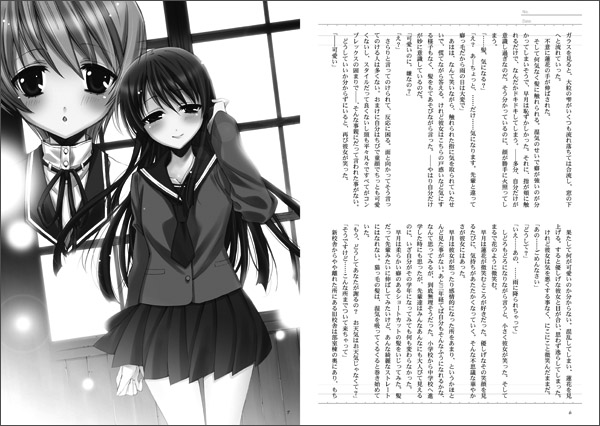 |
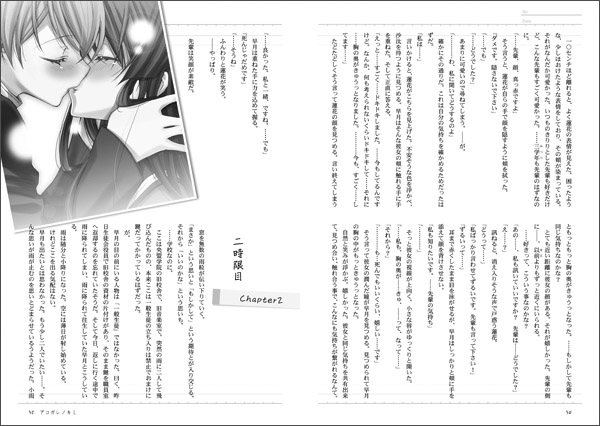 |
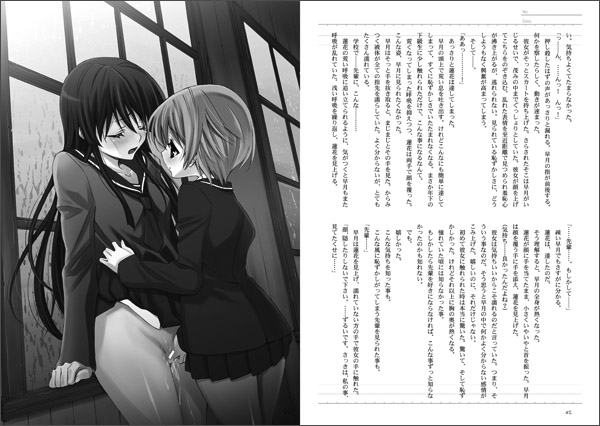 |
|
[HR 〜Prologue〜]
さらりと黒髪が揺れた。 旧い木造の旧校舎は、あくまでも静寂を欲するようにあらゆる音を飲み込んでいく。使われなくなって久しい旧音楽室は、薄暗くひっそりとしていた。 「あ、あの……石動(いするぎ)…せん、ぱい……」 思わず声が震えてしまう。それを悟られまいと懸命に声を絞り出してみるが、名門校のお嬢様らしく動じる事もなく目の前のその人はさも当然とばかりに余裕の笑みを浮かべている。 トレードマークとも言えるさらさらの長い黒髪が、清水が流れ落ちるように肩から滑り落ちていく。それを見つめながら、かすかに香ってくる優しい香りにドキリとした。 標準よりも少し高い背、腰まで伸ばしたさらさらの黒髪は癖なんてなくて、よく手入れが行き届いている。白い肌、長くて細い指先、整った顔立ち、繊細な仕種。 こんな完璧な人が本当にいるなんて思いもしなかった。 ——この人に出会うまでは。 「……早月ちゃん」 二人っきりの旧音楽室でそっと名前を囁かれ、早月(さつき)の心臓が跳ねる。 それが表情に出たのだろう、こちらを見つめる彼女がかすかに笑みを浮かべた。いつだって余裕で、落ち着きがあって、彼女が動じる事なんてないように思ってしまう。自分だけが勝手に緊張しているみたいで、恥ずかしかった。 志津野早月(しづのさつき)にとって石動蓮花(いするぎれんか)は三学年上の——三つも年上の先輩だ。おまけに県下でも一、二を争う進学校である、歴史ある私立央盟学院の生徒会長でもある。年齢の開きはもちろんの事、由緒正しいお嬢様学校の生徒会長である蓮花は、早月にとってなんとなく雲の上のような存在だった。以前は一方的に憧れているだけだったが、知り合った今でさえ、一緒にいるとなんだか緊張してしまう。 けれどその緊張感もけっして嫌いじゃなかった。 長い髪を肩に流す仕種さえ、洗練され、大人びて見える彼女。それに比べて自分は外見も性格も子供っぽくて、おまけに庶民を絵に描いたような完璧な庶民ぷりであり、時折落ち込む事もあるが、そんな小さなコンプレックスさえ忘れてしまう程、一緒にいられるだけで嬉しかった。 彼女が窓の外に視線を向けた。 「雨、小降りになって来たわね」 「そう…ですね。もうすぐしたら晴れるかな」 耳のあたりの髪をなでつけながら窓の外に目を向け、雲行きを見る。雨脚は確かに随分と弱くなっていたが、空はまだ少し暗い。窓ガラスを見ると、大粒の雫がいくつも流れ落ちては合流し、窓の下へと流れていった。 不意に蓮花の手が伸ばされた。 そして何気なく髪に触れられる。湿気のせいで癖が強いのが分かってしまいそうで、早月は恥ずかしかった。それに、指が頬に触れるだけで、なんだかドキドキしてしまう。——多分、自分だけが意識し過ぎなのだ。そう分かっているのに、顔が勝手に火照ってしまう。 「……髪、気になる?」 「え? あ…ちょっと、……だけ……気になります。先輩と違って癖っ毛だから雨の日は大変で」 あはは、なんて笑いながら、触れられた指に気を取られていたせいで、慌てながら答える。けれど彼女はこちらの戸惑いなど気にする様子もなく、髪をもてあそびながら言った。——やはり自分だけが妙に意識しているのだ。 「可愛いのに。嫌なの?」 「え?」 さらりと言ってのけられて、反応に困る。面と向かってそう言ってのける人は多くない。おまけに自分はちびで童顔でちっとも可愛くないし、スタイルだって良くないし頭も平々凡々ですべてがコンプレックスの固まりで——、そんな事親にだって言われた事がない。 どうしていいか分からずにいると、再び彼女が笑った。 「——可愛い」 果たして何が可愛いのか分からない。混乱してしまい、蓮花を見上げる。すると優しげな彼女と目が合い、思わず逸らしてしまった。 けれど彼女は気を悪くする事なく、にこにこと微笑んだままだ。 「あの……ごめんなさい」 「どうして?」 「いえ……あの、……雨に降られちゃって」 しどろもどろになりながら言うと、小さく彼女が笑った。そしてまるで花のように微笑む。 早月は蓮花が微笑むところが好きだった。優しげなその笑顔を見るたびに、気持ちがあたたかくなっていく。そんな不思議な華やかさが彼女にはあった。 早月は彼女が怒ったり感情的になった所をあまり、というかほとんど見た事がない。あと三年経てば自分もそんなふうになれるかな、なんて思ってみるが、到底無理そうだった。小学校から中学校へ進学した時にも思ったが、先輩達はみんなあんなにも大人びて見えるのに、いざ自分がその学年になってみても何も変わらなかった。 早月は柔らかい癖のあるショートカットの髪をいじってみた。髪だって先輩みたいに伸ばしてみたいけど、あんな綺麗なストレートにはなれない。猫っ毛の髪は、湿気を吸ってくるくると巻き始めていた。 「もう、どうしてあなたが謝るの? お天気はお天気じゃなくて?」 「そうですけど……こんな所までついて来ちゃって」 新校舎からやや離れた所にある旧校舎は部室棟の奥にあり、もちろん一般生徒の入室は厳禁だ。 おまけに、先輩とは言っても、蓮花は厳密には本当の先輩ではなかった。 彼女は「私立央盟学院」の生徒であり、早月は「星慶大学附属私立星慶学苑」に通っている。両校は設置母体の学校法人が同じであり姉妹校にあたる上、敷地が隣接しており、生徒間の交流もある。 だが、校内への立ち入りは共有区画以外は許可証が必要だったし、他校の生徒である早月がこんな所にいるのを見つかったらただでは済まない。それは生徒会長である蓮花も例外ではないし、むしろ立場上もっと酷い指導を受けてしまうかも知れない。 けれど蓮花は然したる事でもないように言った。 「いいのよ。それにあのまま雨に降られていたら、二人とも風邪をひいてしまうわ。それに、こんな所、先生だってめったに来ないし、バレないから大丈夫」 不安にさせないためか、優しく微笑む蓮花。 「……はい」 つられるように早月も微笑む。 早月はそんな蓮花が好きだった。 憧れていただけの頃には知り得なかった彼女の色々な姿。真面目さゆえに時に厳しい時もあるが、生徒の長である自覚を常に持ちながらも、ルールに縛られる事なく、柔軟に物事に当たる。 ——つまり、優しいのだ。 優しいお姉さんを絵に描いたような人物(ちなみに早月はこんな人、他に見た事がない)——それが石動蓮花だ。 (……実際三つも先輩だしなぁ) 早月にとって三歳の年齢差はとても大きいように感じる。彼女はとても大人で、それに清楚で可憐で、いわゆるお育ちだって違うように感じる。実際彼女の両親は医者と著名な学者で、早月の平凡な家庭とは比べものにならないほど、裕福なはずだ。——だから「雲の上の存在」なのだ。それに央盟学院自体、新設の星慶学苑とは違い、いわゆるお嬢様も多い。 そんな二人がどうして接点を持ったかと言えば、両校は文化祭などの行事が合同で行われる事もあり、生徒たちの交流は他校とくらべてずっと深かい。その上早月の姉が蓮花の通う央盟学院に通っている事もあり、色々と縁があって今こうしているのだった。 実を言うと、早月はそんなに成績がよろしくない。精々中の中だ。だから本当は姉の通う央盟に入りたかったのだが、当然のように入試は落ちてしまった。そういったわけで、なんとか頑張って星慶に滑り込んだのだ。 そんな自分が、下級生の頃からすでに注目を浴びていた蓮花とお近づきになれたのが、今以て不思議でならない。そんなとりとめもない事を考えていると、不意に声をかけられた。 「早月ちゃん、寒くはない?」 「は、はい。だ、大丈夫……です」 雨に降られたと言っても、本格的に降り出す前に旧校舎へ駆け込んだので、それ程に被害はない。けれど蓮花は優しく早月を引き寄せると、壁際で早月に寄り添った。 「……こうしてるとあったかいでしょう?」 「…………はい」 時に蓮花は、こちらが思いがけもしないような事をする。恐らくあまり世間ずれしていないからだと思うが、こんな風に抱き寄せたり、手を握ったり——。 そのくせこちらがどんなに緊張するのか知ってか知らずか当人は涼しい顔でいたりするから、ますます早月はどうしていいのか分からなくなってしまうのだった。 でも。 「……早月ちゃん」 優しく名前をささやかれる。それだけで気持ちが浮き足立つ。彼女は普段は志津野さんと名字で呼ぶのに、二人っきりになるとこうして名前で呼んだ。 蓮花は一度、早月の声を透き通って綺麗だと言ったが、彼女の方がずっと綺麗な声だと早月は思った。優しくって柔らかくって、落ち着きがあって、なんだかしっとりした声で、でも、時々、今みたいに高くなる。濡らした指でグラスをこすって音を鳴らすガラスハープみたいだ。 そんな蓮花の顔がすぐ横にある。 何度か、こんなふうに近くで彼女の顔を見た事もあったが、とても綺麗で、その度に何だかドキドキしてしまうのだった。ここが央盟の旧校舎の音楽室だとか、放課後二人っきりだとか、もしかしたら誰か来るかもしれないとか——。そんな事がぐるぐると頭を過ぎるが、結局気持ちが浮き足立つのにまかせて、理性と共にふわふわとどこかへ飛んでいってしまう。 「あの、せんぱ……」 「早月ちゃん……」 小さく名前をつぶやく蓮花。 そして大きな制服から指先だけがのぞく早月の手に、細く長い指をからめた。 目が合った途端、心臓が早鐘を打ち始め、胸が苦しくなる。早月は——ぎゅっと拳を握った。 『それ』が何を意味するか。 『そんな事』を心のどこかで期待してしまうようになったのは、一体いつからだったろう。いつも遠くから彼女を目で追い、二人で話が出来るようになった時はそれだけですごく嬉しかったのに。 「先輩と話が出来た」「先輩と仲良くなれた」、そう姉に報告しながら些細な事で喜んで、落ち込んで、——それだけだったのに。 気がついたら「憧れ」から「好き」へと気持ちが変わっていた。 合同合唱祭の都合で、合唱部の先輩から言づけを頼まれ、初めて言葉を交わし、それから少しずつ距離が縮まった。でもそれはただ先輩と後輩としてで。——ちょっと仲の良い、先輩と、後輩。 ——それだけで。 でも———— 違った。 初めはこの気持ちがなんなのか分からなかった。——でも、彼女と生まれて初めてキスをして——。こんな気持ちがある事を知った。 しとしとと雨が土の地面を叩く。旧校舎は部室棟の奥にあり、立ち寄る者はほとんどいない。 壁に寄りかかったまま、蓮花が身体を寄せて来る。壁に手をついて、体重がかからないように気を使ってくれているのが分かった。 そしてためらいながらも柔らかな口唇が、————そっと触れる。 その感触に、それだけで恍惚となった。柔らかくてあったかくて、——何も考えられなくなる。 ゆっくりと唇が離れた。 それから蓮花が頬を染めながら、はにかんで言った。 「ごめんなさい。……学校なのに」 そう言ってそっと視線を逸らす。早月はそんな蓮花は滅多に見られないので、学校だと言う事なんてどうでも良くなって笑った。 「……いいです。誰も……いないし」 「……そうね」 まだ恥ずかしいのか、冷えた手で火照った頬を冷やす蓮花。大胆なようで、こと恋愛に関しては恥ずかしさが先に立ってしまうようで、キスだってしてくれるくせにこんな風に恥ずかしがってしまう。 でも早月はそんな蓮花も好きだった。 普段の生徒会長然とした「みんなの憧れ」の先輩もやっぱり好きだったが、二人きりの時に見せる、こんなちょっと照れ屋な彼女も好きだったから。 早月は誰もいないと分かりつつもついつい周りを確認してから、彼女のもう一方の頬に手を当てた。蓮花ほどは冷たくない手だが、十分に彼女の頬を冷やしてくれる。 学校でこんな風にするなんて、なんだかドキドキした。 学校や街ではいつも人の目を気にしなくてはならなかったし、普段なら手を繋ぐ事すらままならないのに。こんな風に触れ合えるなんて、なんだか嬉しかった。 けれど、次にこう出来るのはいつだろう。そう思うと離れがたかった。 通う学校が違うせいで平日は顔を合わせる事もままならないし、週に一度、共有区画の談話室で一緒にお弁当を食べる約束はしているものの、生徒会の都合でそれすらつぶれてしまう事もあった。それに談話室は常に人の目があり、手を握る事も出来ない。 放課後は早月には部活がある。蓮花にも生徒会の都合がある。 もどかしかった。 本当は毎日でも会いたいのに。 学校にはいるのだから近くにいるはずなのに。 それは蓮花も同じ想いなのだろう。 少し潤んだ彼女の瞳がこちらを見下ろす。 頬に触れた手に手を添える彼女。早月の指の間に指を這わせ、ゆっくりと握り込んでいく。 早月の手の甲に、手のひらが押しつけられる。 ゆっくりと瞳が伏せられる。 ずっとそのままでいたかった。触れ合って、熱を確かめ合って。人の目なんて気にする事なく想いを確かめ合いたかった。 「……ごめんね」 それは小さな声だった。突然謝られて心当たりのない早月は、大きな丸い瞳をぱちぱちとしばたたかせた。 「ど…して謝るんですか?」 「……私が、あなたを好きになってなってしまったから……。こんな風にしか会えないし、なんだか、こそこそするみたいで、ごめんなさい……」 それを聞いて、早月は混乱すると同時に少しむっとした。そして蓮花が言いかけた言葉を強く遮る。 「どうしてそんな風に言うんですか?」 少し強い声が出た。 「先輩だけじゃなくって、私だってちゃんと先輩の事が好きです。そんな、先輩のせいみたいに言わないで下さい。私、別に先輩に言われたから先輩を好きになったわけじゃないです。そりゃ確かに今まで人を好きになった事なんてなかったけど、でもちゃんと、ちゃんと先輩の事が好きです! こそこそしてたっていいですよ。確かに先輩は生徒会長としての立場があるかも知れないけど……!」 蓮花は常に人の目を気にしていた。立場ある身だからといつも自らを律していたし、不用意にべたべたしたがる早月をいさめたりする事さえある。でも早月はそうされるのが嬉しかったし、優しく叱る蓮花も好きだったのだ。 彼女は生真面目だ。時にそれが過ぎる事もあるが、その分二人きりでいられる時間は甘えるような素振りを見せる事すらあって、そんな彼女が大好きだった。 そんな風に言って欲しくなかった。どうして、という想いが駆け巡る。確かに告白された時はとても驚いたけれど、今のこの気持ちは本物だった。 「好きです、先輩の事が……」 けれどムキになればなるほど、声が高く上擦り、ずっと子供っぽくなってしまう。それも嫌だった。 本当は喧嘩なんてしたくなかった。せっかく二人きりでいられる時間を大事にしたかった。 「先輩……」 彼女を呼び、少し冷え始めた唇にキスをする。 自分からしたのはとても久し振りだった。多分、あの時以来だ。先輩はこちらがねだるような素振りを見せれば、必ず優しいキスをくれたから——。 それはただ押しつけるだけのキスだったが、なんだか緊張した。離れていく唇に彼女の吐息がかかる。 「……うん。……ありがとう、早月ちゃん」 「ちゃんと、先輩も言って下さい」 そう言うと彼女が優しい笑顔を見せた。 「……好きよ。……大好き。誰よりも好きよ」 そして頬に触れた手のひらの唇に近いあたりに、そっと唇を押しつけられた。 それだけなのに、胸が締め付けられるような気がした。——違う。そうじゃない。締め付けられるんじゃなくて、もっと違う感覚だった。 唇にされているわけじゃないのに、彼女の気持ちが伝わって余計にドキドキしてしまう。 蓮花が手のひらについばむようなキスをしていく。優しく唇で挟み込むように。時に押しつけるように。時に、————感触を味わうように。 時折、小さな音がした。 手元を見つめ、蓮花が丁寧にキスをする。それだけなのに。実際に唇にキスをされているわけじゃないのに、早月の鼓動はどんどん速まっていく。 早月は思わず小さく足を踏み出していた。そしてその分だけ蓮花と近づく。ゆっくりと上体を起こす。 ——もっと、して欲しかった。 次に二人で会えるのはいつ? 次にキスしてもらえるのはいつ? 蓮花がかすかに顔を上げた。 もう少し身体を近づける。それからねだるようにそっと首を傾げた。おねだりをすれば、彼女は必ず応えてくれる。きっと、ずるいのは自分だ。先輩が困るのが分かっているのに、たくさんねだってしまう。 背筋を伸ばす。唇が近づく。 そして、 ——唇が触れ合った。 その瞬間、蓮花が少し角度を変える。伺うようにしながら優しくはむ唇の感触が心地良くて、早月はそっと目をつぶった。長くて綺麗な黒髪がサラサラと落ちて来て、頬をくすぐるのさえ心地良い。 やがて口づけが深くなった。突然の事に胸の奥がきゅっとなる。 初めての深いキスのその感触に、深くなった分、早月の鼓動も速まっていく。 不思議な感覚だった。あたたかくてなんだかぬるっとしている。 けれど深いのにとても優しかった。決して無理矢理舌を進ませるような事もなく、優しく導いていく。やわらかく巻き取られた舌がやんわりと吸われ、形を変える。 早月の下唇を口に含む蓮花。その拍子にしなだれかかるように身体がこちらに寄せられる。壁についた手がさらに奥まった所につかれて、さっきよりもずっと密着した。 「ん……」 蓮花の艶やかな高い声が耳をくすぐる。その初めて耳にする声に、ドキリとして身体の奥がしびれた。 唇と同時に舌が下唇をなでた。 「…んっ……」 声が出てしまい、恥ずかしくなって手をきゅっと握りしめる。 「せ……せんぱい……」 恥ずかしさのあまり呼びかけると、彼女が少し身を引いて、お互いの唇の間を糸が引いた。その糸がぷつりと途切れる。 「あの……」 「嫌……だった?」 蓮花が心配そうに尋ねる。早月は首を振って、それから彼女の制服の胸元をきゅっと掴んだ。嫌なんかじゃない。本当はもっとして欲しかった。でも、そんな事言えなくて、弱々しく制服を掴むしか出来なくなる。 「……早月……ちゃん?」 優しく気遣うように先輩が声をかける。そう、先輩はいつだって優しい。優しくて、綺麗で、皆の憧れで——。 でも、私のものだ。 「……っと」 「……え?」 「……もっと、……て…欲しい、です」 「え?」 驚いた顔の先輩が目の前にあって。もう顔から火が出る思いがした。本当はこんな事言いたくない。でも、気がついたら口にしていた。先輩が、嫌、なんて聞くから。そんなはずあるわけないのに。 「先輩、もっと、そういうの、して下さい」 思い切ってもう少し大きな声で言った。すると彼女が遠慮がちに言った。 「……もっ、と?」 蓮花の声にこくりと頷く。真っ直ぐに彼女の目を見て言う。 「嫌なはずないです。すごくドキドキして……もっとたくさんして欲しいです。いっぱい先輩にして欲しいです」 潤んだ瞳が葛藤するように何度かしばたたかれる。 そしてゆっくりと唇が近づく。 「好き…よ、早月ちゃん……」 小さな声で囁かれ、唇をふさがれる。いつもの優しいキス。だけど口唇が開いて、そして——。 優しい雨音がいつまでも続いていた。 To be continued. |